このたび厚生労働省「院内感染対策中央会議」において院内感染対策についての提言
2) がまとめられた。本提言を受けて、2011 年6 月17 日に厚生労働省医政局指導課長通知「医療機関等における院内感染対策について」
3) が発出された。この中で、院内感染のアウトブレイクが初めて定義され、医療現場での対応に加え、保健所への届け出の目安も示された。
2-1. 院内感染のアウトブレイクを疑う基準
1 例目の発見から4 週間以内に、同一病棟において新規に同一菌種による感染症の発病症例(以下の4 菌種は保菌者を含む:バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(Vancomycinresistant Staphylococcus aureus: VRSA)、多剤耐性緑膿菌(multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa: MDRP)、バンコマイシン耐性腸球菌(Vancomycin-resistant Enterococci: VRE)、多剤耐性アシネトバクター・バウマニ(multidrug-resistant Acinetobacter baumannii: MDR-Ab))が計3 例以上特定された場合。
2-2. 医療機関内の初動対応
アウトブレイクが疑われると判断した場合、感染対策委員会又はインフェクションコントロールチーム(infection control team: ICT)の会議を開催し、1 週間以内を目安にアウトブレイクに対する院内感染対策を策定かつ実施する。
2-3. 地域ネットワークへの支援要請
アウトブレイクに対する感染対策を実施した後、さらに該当感染症の発生(上記の4 菌種は保菌者を含む)を認めた場合、院内感染対策に不備がある可能性があると判断し、速やかに協力関係にある地域のネットワークに参加する医療機関等の専門家に感染拡大の防止に向けた支援を依頼する。
2-4. 管轄保健所への報告
医療機関内での院内感染対策を講じた後、同一医療機関内で同一菌種による感染症の発病症例(上記の4 菌種は保菌者を含む)が多数にのぼる場合(目安として10名以上となった場合)または当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合においては、管轄する保健所に速やかに報告する。また、このような場合に至らない時点においても、医療機関の判断の下、必要に応じて保健所に連絡・相談することが望ましい。
2-5. 保健所の対応
報告を受けた保健所は、当該院内感染発生事案に対する医療機関の対応が、事案発生当初の計画どおりに実施され効果を上げているか、また地域のネットワークに参加する医療機関等の専門家による支援が順調に進められているか、一定の期間にわたり定期的に確認し、必要に応じて指導及び助言をおこなう。その際、医療機関等の専門家の判断も参考にすることが望ましい。
さらに、保健所は、医療機関からの報告を受けた後、都道府県や政令市等と密接に連携をとる必要がある。
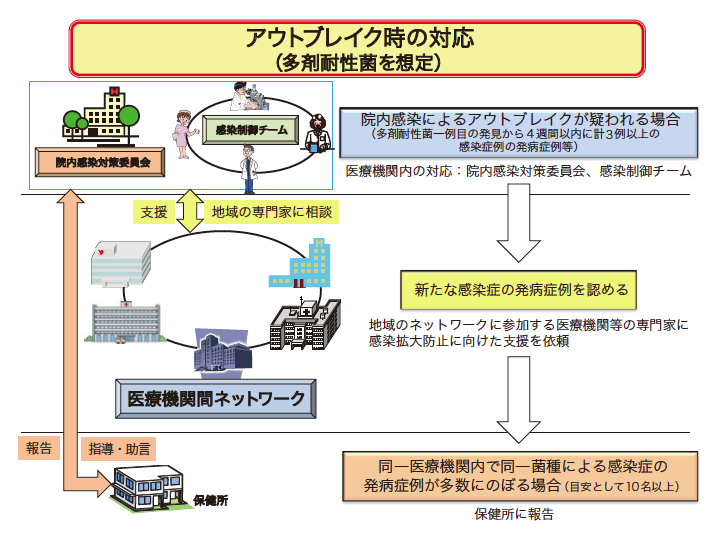 図1)アウトブレイク時の対応(多剤耐性菌を想定して) 資料6)より改変引用
図1)アウトブレイク時の対応(多剤耐性菌を想定して) 資料6)より改変引用